本文
【NPO活動に寄付を!登録団体一覧】ふるさとくまもと応援寄付金で活動を応援しましょう
ふるさとくまもと応援寄附金で寄付が可能なNPO法人団体を紹介します。応援したい活動を探してみませんか。
1 制度の概要
地域の様々な課題解決に向けて公益的な活動を行うNPO等を支援するため、「ふるさとくまもと応援寄附金(ふるさと納税)」を活用して、支援対象となるNPO等への寄附金受付を行っています。
※ 県では、熊本県を応援してくださる方々から「ふるさとくまもと応援寄附金(ふるさと納税)」を募集しており、寄せられた寄附金は、寄附をしていただいた皆様の希望に応じ、県政における様々な取組みに使わせていただいています。
「ふるさとくまもと応援寄附金(ふるさと納税)」のメニューに「NPO等支援分」を設け、まちづくりの推進や、災害時の救援、子どもの健全育成といった、地域における様々な課題の解決に向けて公益的な活動を行っているNPO等の非営利団体を支え、「くまもと」の持続的な発展に繋がるよう、支援の対象となるNPO等への寄附金を受け付けています。
寄附をお申込みいただく際、寄附金の使途を「NPO等支援分」とし、登録されたNPO等の一覧の中から応援したい団体を指定した上で寄附いただくと、県から指定された団体へ寄附金の2分の1が交付され、その団体の公益的な活動に役立てられます。(特に指定がない場合は、県全体のNPO等を支援する事業等に活用されます。)
1 寄附のお申込先等
県HP(URL:https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/16/50519.html)
※ 寄附金の使いみち(NPO等支援分):県HP(URL:https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/16/50515.html)
地域課題を行政・民間とともに解決しようと頑張っているNPO法人等を応援しましょう。
※団体名をクリックすると、団体の活動内容ページが見れます。
※順不同です。
| 団体名 (登記上) |
主たる事務所の所在地 (登記上) |
代表者氏名 | 設立(登記) 年月日 |
分野 |
| 一般社団法人熊本私学教育支援事業団 | 熊本市中央区大江3丁目6-8 三祐ビル2階 | 仙波 達哉 | H22.3.4 | 教育 |
| 公益財団法人 ほしのわ | 熊本市中央区桜町3番10号 Sakuramachi Kumamoto 5階 | 本郷 秀之 | H30.3.26 | 教育 |
| 特定非営利活動法人 熊本子どもの本の研究会 | 熊本市東区西原1丁目15番24号 | 横田 真 | H23.10.3 | 教育 |
| NPO法人くまもとゼロスクール | 上益城郡御船町大字豊秋1874番地3 | 園田 美由紀 | H31.3.20 | 教育 |
| 公益財団法人 鶴友奨学会 | 熊本市中央区手取本町6番1号 鶴屋百貨店内 | 久我 彰登 | S49.3.22 | 教育 |
| 一般財団法人くまもとSDGs推進財団 | 熊本市中央区安政町3番13号 熊本県商工会館内 | 徳永 伸介 | R1.8.23 | 環境 |
| 特定非営利活動法人九州バイオマスフォーラム | 阿蘇市一の宮町宮地5816 | 藥師堂 謙一 | H15.12.17 | 環境 |
| NPO法人地球と共に生きる会 | 主たる事務所:神奈川県厚木市長谷987番地4 従たる事務所:天草市天草町高浜北2570 |
渡邉 政男 | H14.7.22 | 環境 |
| NPO法人熊本県海難救助隊 | 熊本県八代市高下西町799-11 NPO法人熊本県海難救助隊事務局 | 木村 博幸 | H23.9.20 | 危機管理 |
| 特定非営利活動法人れんげ国際ボランティア会 | 玉名市築地2288 | 川原 英照 | 2003年4月8日 | 国際 |
| NPO法人外国から来た子ども支援ネットくまもと | 合志市須屋3120番地9 | 竹村 朋子 | H26.10.27 | 国際 |
| NPO法人犬猫ケアホームきずなの丘 | 熊本県阿蘇郡西原村大字河原2003番地1 | 上野 好江 | H29.10.18 | その他 |
| 公益社団法人くまもと被害者支援センター | 熊本市中央区水前寺六丁目9番5号 | 高木 絹子 | H15.4.1 | その他 |
| 特定非営利活動法人 Searchdog人吉 | 球磨郡相良村大字柳瀬315番地2 | 開田 宏 | R3.4.26 | その他 |
| 特定非営利活動法人熊本県バドミントン王国復活プロジェクト | 熊本市中央区内坪井町4-8熊本県バドミントン協会内 | 木村 洋一郎 | R4.4.1 | その他 |
| NPO法人はっぴぃ・はっぴぃ | 熊本県菊池郡大津町大字陣内1652番地 | 江藤 南美枝 | H23.5.27 | 地域 |
| NPO法人せいしとらんし熊本 | 熊本市北区徳王二丁目1番48号 | 中村 和可子 | R1.11.11 | 地域 |
| NPO法人くまもと文化財プロジェクト | 上益城郡嘉島町大字上六嘉2035番地 | 大塚 浩平 | R1.10.1 | 地域 |
| NPO法人オハイエくまもと | 熊本市中央区山崎町8-8 Rkk別館4F | 入部 祥子 | H25.9.2 | 地域 |
| 公益財団法人阿蘇地域振興デザインセンター | 阿蘇市一の宮町宮地4607番地1 | 渡邉 誠次 | H2.5.30 | 地域 |
| NPO法人A-lifeなんかん | 熊本県玉名郡南関町大字小原1857番地 | 原口 護 | H24.7.25 | 地域 |
| 特定非営利活動法人熊本子ども囲碁普及会 | 熊本市東区佐土原1丁目10番1号 | 奥薗 惣幸 | H25.7.30 | 地域 |
| 一般社団法人熊本暮らし人まつり | 熊本市中央区水前寺1-6-41 Ocoビル903号 | 石原 靖也 | H26.8.4 | 地域 |
| 特定非営利活動法人山鹿きぼうの家 | 熊本県山鹿市古閑1160番地 | 米岡 𠮷春 | H18.7.4 | 福祉 |
| 一般社団法人Arts and Sports for Everyone | 熊本市中央区帯山五丁目38番23号 | 吉田 祐一 | H29.5.10 | 福祉 |
| 特定非営利活動法人スペシャルオリンピックス 日本・熊本 |
熊本市中央区千葉城町5-50 熊本メディアビル4F |
米満 弘一郎 | H15.1.17 | 福祉 |
| NPO法人トナリビト | 熊本市西区上熊本二丁目15番16号 | 山下 祈恵 | R2.2.28 | 福祉 |
| 社会福祉法人熊本いのちの電話 | 熊本市中央区迎町一丁目4番20号 | 福田 稠 | H7.6.1 | 福祉 |
| 特定非営利活動法人ブリッジフォースマイル | (主)東京都港区南青山3-1-30 (従)熊本市中央区辛島町6-2ペアレントビル9階901 |
林 恵子 | H17.6.8 | 福祉 |
| 特定非営利活動法人自立の店ひまわりパン工房・カフェ | 熊本市中央区国府1丁目13番8号 | 牧野 智子 | H21.12.17 | 福祉 |
| 特定非営利活動法人優里の会 | 熊本市東区桜木5丁目9-102-B | 黒田 信子 | H25.1.30 | 福祉 |
| NPO法人ガット | 熊本市西区中島町1279番地6 | 西村 るり | H29. 2.22 | 福祉 |
| 熊本市中央区東子飼町8番43号 | 内賀島 守 | H19.1.25 | 福祉 | |
| 特定非営利活動法人自立応援団 | 熊本市北区貢町780番地8 | 福島 貴志 | H14.1.23 | 福祉 |
| 認定NPO法人とら太の会 | 八代市妙見町2377-3 | 山下 順子 | H15.4.1 | 福祉 |
| 特定非営利活動法人くまもとライフボート | 熊本市東区花立5丁目4番78号 | 馬場 厚 | 1999年10月1日 | 福祉 |
| NPO法人ひのくにスマイルプロジェクト | 菊池市泗水町吉富300-61 | 茶木谷 与和 | R6.4.18 | 福祉 |
| 阿蘇郡南阿蘇村大字203番地1号 | 吉村 孫德 | H15.11.6 | 地域 | |
| 一般社団法人水俣青年会議所 | 水俣市大園町1-11-5 水俣商工会館 2F | 竹田 瑠典 | S60.12.27 | 地域 |
| 特定非営利活動法人熊本県地域こども食堂支援センター Tsudou・Net | 熊本市中央区帯山4丁目24-23 | 野村 順子 | R6.1.25 | 福祉 |
「学びの多様化学校(不登校特例校)」設立に向けて皆さまのご支援お願いいたします!
不登校・ひきこもりの支援活動を始めて16年、「熊本学習支援センター」は、2025年4月から、天草下田校改め「学校法人 小田床学園(こざとこがくえん)」を設立する運びとなりました。
熊本では、初の「学びの多様化学校」(不登校特例校)となり、認可申請中です。近年、不登校の数は増加の一途を辿り、毎年過去最高の数となっております。不登校の生徒たちはそれぞれに困難を抱えて、心休まる場を探し求めています。ここ小田床学園は、木造りの光あふれる校舎、豊かな海と緑の自然の中でのびのびと過ごし、主体的な学びができます。
現在、居場所を失い、社会へ踏み出すことができない子どもたちが大勢います。このような子どもたちを自立出来るようにサポートしなければ、社会にとって甚大な損失以外何ものでもありません。子どもたちは、これからの未来を創る大きな宝です。まだまだ設立にあたり、財政的にも盤石ではありません。皆様方のご支援とご協力を賜らざるを得ません。何卒、未来を創る子どもたちへのご寄附をよろしくお願い申し上げます。 設立代表理事 仙波 達哉


2023年8月 天草下田南校内の大ホール
熊本学習支援センター天草下田南校の
開校式の様子
当財団は熊本県内の大学・高等専門学校・専修学校に在籍し、経済的な理由で就学が困難である優秀な学生に対して、返済不要の奨学金を支給しています。
熊本地震をきっかけに、2018年に地元出身の経営者本郷秀之により設立され、これまでに延べ86名の学生を支援して参りました。
2023年からは、高校3年生を対象に、大学等への進学後の奨学金を予約できる「予約奨学生制度」もスタートしています。
一人でも多くの熊本の学生が充実した学校生活を送ることができるよう、皆様の御支援をお願いいたします。

熊本の学生に返済不要の奨学金を
支給して就学を支援しています。
特定非営利活動法人熊本子どもの本の研究会
1983年5月以来、熊本子ども本の研究会は、読書活動や体験活動を通して、子ども達が本に親しむとともに、地域・日本を超えた幅広い知見と視野を持てるようになることを目的として活動しています。当研究会の現在の活動については、ホームページ(https://kodomonohon.org/welcome/)をご参照願います。会報(年6回発行)も掲載しています。
2025年度は、公開講座「日本の昔ばなしを読む」(講師:森正人熊本大学名誉教授)を始めとする講座を毎月開催する他、オンライン活動として、子どもと大人の読書会、グリム童話の魅力、昔話の基本文献を読む会を開催します。
依頼に基づき、支援学校、図書館、小学校、公民館等でのおはなしボランティアも行っています(2024年度は27回開催)。
地域の子ども達を対象に研究会事務所(熊本市東区西原)に併設されている「びわの木文庫」(児童書6千冊程を含め1万冊ほど所蔵)からの本の貸出も行っています。昨年度より、小学校の学童クラブ及び公民館に数十冊単位で長期貸出するサービスも初めています。今後貸出先を増やしていきたいと考えています。
研究会の活動へご参加いただくことをも含め、ご支援方宜しくお願いいたします。

「びわの木文庫」
研究会事務所2階に併設
くまもとゼロスクールは、令和元年5月に御船町に開校したオルタナティブスクール(公教育とは異なるもう1つの学校)です。
現在、熊本県内で御船本校・熊本市の錦ヶ丘分校・菊池分校・玉名分校の4校を運営しており、50名以上の子どもたちが毎日元氣に通って来ています。
無限の可能性を持っている子どもたちは「ゼロ」そのもの。
そのまんまで天才。
そんな子どもたちが、大好きなことをとことん楽しみ、とことん追求し、本来の自分の能力を最大限に発揮できるような、子どもから大人までの素敵な学校を熊本に創りたい!
そんな願いからゼロスクールは生まれました。
現在、民間のフリースクール等に関しては行政からの支援等が無い状況で運営しています。
これからの未来を創っていく子どもたちのために、ご支援どうぞよろしくお願い致します。

地球の循環をテーマにした環境創り
鶴友奨学会(かくゆうしょうがくかい)は、1974年に設立され、2024年に50周年を迎えました。これも皆様の温かいご支援の賜物であり、心より感謝申し上げます。
当財団は熊本県内の高等学校・高等専門学校・大学で学ぶ意欲ある学生に十分な学習環境を提供したいという願いにより創設され、2014年からは、給付型奨学金制度に移行し、高校生には月2万円、大学生には月3万円を給付し、毎年20名以上の奨学生を支援しております。
奨学生の約8割はひとり親世帯であり、ほかにも、親が障がいを持ち十分に働けない世帯や、生活保護を受給している世帯など、厳しい家庭環境の学生が含まれます。経済的な理由から進学や夢の実現を諦めざるを得ない学生も少なくなくありません。
一人でも多くの学生の支援に繋げるため、当財団の趣旨にご賛同してくださる方々からの寄付金を募っております。温かいご支援とご協力をお願い申し上げます。


2024年8月18日に開催した鶴友奨学会50周年式典 奨学生代表謝辞の様子
地域課題解決のため個人・企業からのご寄付で県内の多様な社会課題への活動をサポートする市民コミュニティ財団として、持続可能な地域社会づくりに貢献しています。
コロナ感染症拡大時は、困窮するひとり親家庭のために緊急支援を行い、2020年の球磨川豪雨災害では復旧・復興に取り組む団体の活動を支援しました。
その後、球磨川での水害拡大の一因が流域の山の荒廃にあることが明らかになり、早急に森林再生に取り組むために2023年に「豊かで災害に強いふるさとの森づくり基金」を創設。森林再生に取り組む団体への助成事業を開始し、基金創設2年間で、土砂崩れを起こさない持続可能な林業として注目される自伐型林業の道づくりや、皆伐された山を緑豊かな森に蘇らせる活動に取り組む計4団体を支援、ふるさと熊本の森林再生を推進しています。
森林面積が6割を超える熊本県の森林再生活動が市民に広がり、広く定着していくためには、持続的な資金調達が大きな課題です。ふるさと納税でのご支援をどうぞよろしくお願いいたします。


皆伐された山を緑豊かな森に蘇らせる活動。「風の杜」が実施した観察会の様子。
(球磨郡多良木町)
「城内生産森林組合」が基金の助成を受けて整備した、土砂崩れを起こさない自伐型の林道。
(球磨郡山江村)
私たちの身近にある資源を有効活用することは、地球温暖化対策や持続可能な社会の形成にとって大切です。阿蘇地域には豊かな森林資源や、広大な草原の草資源があります。NPO法人九州バイオマスフォーラムでは、バイオマスの普及を目指し、これらの資源の利活用を進めてきました。
森林整備の過程で発生する間伐材や、建築材として利用できない雑木(時には災害木)などを森林組合や林業事業者から買い取り、薪に加工し販売しています。また、間伐材を利用し、会員や地域住民に向けた薪割り体験イベントを実施しています。
地域の特長を生かした資源循環型の仕組みを作ることで、環境保全と地域経済の活性化の両立に貢献していきます。
頂いた寄附は、薪生産などに必要な備品の購入やイベント等の運営費用に使わせて頂きます。


薪割り体験イベントで森林・林業についての講話を行う様子
薪割り体験を行う様子
2000年に任意団体として発会した「地球と共に生きる会」は、2002年にNPO法人の認可を受けてより、一貫して「青少年の健全育成」「食の改善と確保」「自然環境保全」に取り組み続けています。当法人が2014年より事務局を務める「Fujisan地球フェスタWa」では、「未来の子ども達に美しい地球と和の心を残したい」というテーマのもと、日本の伝統文化であるお田植え祭・収穫祭を通して、稲作漁労文化に残された「大自然と人と人々が共に和して生きる」という生き方を広く啓発しています。
みんなの富士山のネットワークを通じて、全国・全世界の被災地復興、防災(災害予防・対策)への啓蒙と、親子稲作体験で大地と触れ合うことにより、次の時代を担う青少年と都市生活者の心身の健全育成に寄与すること及び食の改善に向けて、大地と体に優しい食物の生産と流通の拡大のため、玄米粉料理ワークショップを開催し、農家と消費者との相互依存による支援と村おこしを目指し、それに伴う農業従事者の育成をすること、そして、ふるさと納税に参画することで、米農家の支援と青少年の健全育成への活動を進めることを目的としています。

親子稲作体験 お田植え祭(阿蘇市・産山村)
本隊は、国内では3番目に当たる昭和48年6月に発足し、約47年間活動を続けています。隊員は現在35名、パトロール艇13隻です。
又、県内には海上保安庁より指定を受けた海上安全指導員が26名いますが、その内隊員は半数以上の17名在籍しています。活動は県内の八代海・有明海において海難事故を未然に防止するため、海上安全に関する啓発活動としてチラシ配布、ライフジャケット着用の指導や海上安全パトロールを行っています。
また、豊かな海洋環境作りと、きれいな海を未来に残すために、海水浴場や港湾の清掃ボランティア活動、将来のシーマンリーダー育成事業として毎年夏休みに小中学生を対象にした体験クルージング・航海訓練も実施しています。
近年では、八代港における大型クルーズ客船の海難事故を未然に防ぐため、早朝5時頃より客船の前路警戒とパトロールを行ない、微力ながら海上の安全と併せてクルーズ客船へのおもてなしも行っています。
隊員は、小型船舶免許はもとより、海上安全指導員、看護師、海上特殊無線技士、アマチュア無線技士、工事作業の警戒船業務・管理講習受講者、スクーバー、潜水士等の資格保有者が多数在籍し、日々研鑽しています。

安全啓発パンフレット配布の様子
1980年の設立以来、国境を越えた教育・福祉に関する活動を行ってきた認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)です。カンボジア難民支援から始まり、タイ、スリランカ、インド、ミャンマーなど主にアジアの途上国で、図書館や学校の建設といった教育を中心とする活動を行ってきました。貧困や差別で厳しい状況に置かれた人々の生活や教育の向上を願い、自立のための支援活動を続けています。
また、災害復興にも力を入れており、国内においては島原普賢岳噴火(1991年)での支援から始まり、近年では熊本地震(2016年)、熊本豪雨(2020年)、能登半島地震(2024年)などで、現地での直接支援、もしくはパートナーを介しての支援を行ってきました。ウクライナ避難民支援活動(2022年)では玉東町との官民タイアップで、避難民への支援にとどまらず、地域住民との国際交流活動もサポートし、多文化共生マインドの育成機会の創出に力を入れました。
現在の主な活動地はインドの貧困地区及び僻地で、行政の手が行き届かない学校やインフラの整備を行う一方、教育や衛生に関する啓発活動を通して、ハード及びソフト両面からの支援で自立を促す活動を行っています。

現在活動中のインド貧困地区の子供たち
親とともに来日した日本語が分からない外国ルーツの子供達が増えています。私たちは2009年5月に【熊本県に編入する全ての外国ルーツの子どもに日本語指導を!】という目標をかかげて当会を立ち上げました。2024年現在、県内16市町村(2024年度)の小中学校に日本語教育の資格を持った日本語指導員(30名)を派遣しています。日本語指導以外にも多方面で子どもたちを支えています。
<活動内容>
1)日本語指導「くまもとこどものにほんご」
2)進路サポート「外国ルーツの生徒と保護者のための進路ガイダンス」
3)仲間づくり「県内在住の外国ルーツの中高生の交流会」
4)学習支援と居場所づくり「おるがったステーション」(熊本市国際交流会館)「Globalterakoyaたけんち」(合志事務局)「やまが日本語クラブ」(山鹿隣保館)
5)研修会/講演会
「外国ルーツの子どもたちの現状や多文化共生について」
子どもたちは言葉や文化が違う環境の中、家庭や学校で様々な悩みを抱えています。私たちはそんな子どもたちに寄り添う活動をこれからも続けて参ります。みなさまの温かいご支援をよろしくお願い致します。


第16回九州外国ルーツの生徒交流会in熊本
当法人会で活動している日本語指導員
熊本県阿蘇郡西原村。当団体は阿蘇の雄大な自然に囲まれた素晴らしい場所にあります。”行き場のない犬猫たちを1頭でも多く救いたい”同じ思いを持つボランティアさん達の力を借りながら、日々活動をしています。
犬猫たちの元気に生きる姿を通してたくさんのパワーをもらい、それが私達の活動の原動力にもなっています。人と動物の共生を目指し、両者をつなぐ場所であり続けること。それが動物愛護分野における当団体の役目だと思っています。
より多くの方に私達の活動を知ってもらい、動物愛護について考えるきっかけとなってくれることを願います。

日向ぼっこ きずなの丘にて
当センターは犯罪や交通事故の被害者やその家族及び遺族が、一日でも早く穏やかな生活を取り戻せるよう、電話等による相談や病院受診、法律相談への付添いなど、被害者の方々に寄り添ったサポートを行っています。
また、県の委託を受け、性暴力被害者のための24時間ホットライン「ゆあさいどくまもと」を運営しています。
皆様のご支援をよろしくお願いいたします。


犯罪被害者週間事業(シンポジウム)の様子
北区こどもまつりにて広報啓発活動の様子
当法人は、2021年4月に設立認証され、近年増加する行方不明者をより効果的に捜索救助できないものかと考え、九州各県における嘱託警察犬指導士の有志が県境を越えて集まりました。
その主な活動内容は、
(1) 行方不明者の捜索救助
(2) 警察犬、捜索救助犬の育成
(定期的に実践的な訓練会の実施)
(3) 退役犬の保護管理
また、防災訓練等の参加や活動のPRイベント、教育機関等での講演、各消防や警察との合同訓練会などにも参加し「人犬一体」をモットーに活動しております。
すべての活動は、ボランティアでおこなっています。ご支援のほどよろしくお願いします。
ぜひ、ご支援、ご協力お願いいたします。


訓練中のバディ達
水害による被災地での行方不明者の捜索
「世界No.1への挑戦!
熊本県を再びバドミントン王国へ!」
熊本は1970年代頃までは、「バドミントン県」としてこれまでに数多くのオリンピック選手や全国でもトップの選手を輩出した「バドミントン王国」でした。当団体は、熊本県を本拠地として世界で活躍する再春館製薬所バドミントン部のご協力を得て、熊本から世界ナンバーワンへ挑戦し「バドミントン王国」として熊本を復活させることを目指します。
現在は、小中学生に向けたバドミントン教室やジュニアトップ選手を育成するジュニアアカデミーの開催、ジュニア選手の海外遠征を行い、海外のジュニア選手と交流する国際交流事業、国際大会やパラバドミントン大会への支援など、熊本県のバドミントンにかかわる活動を幅広く行っています。
熊本のジュニアプレーヤーの日本一という夢を具現化すること。そして、まだまだ、普及が必要な障がい者バドミントン競技のさらなる活性化などバドミントン界全体の発展にも大きく寄与することを目的としております。
何卒、主旨にご理解とご賛同いただき、ご協力いただきますようお願い申し上げます。


実業団選手を講師に迎えたバドミントン教室
台湾に選手を派遣し現地の選手と交流を行った 国際交流事業
熊本県の「認定」NPO法人で公益性の高い団体。よかボス宣言を行った「よかボス企業」。
幸せ探しに出逢いの場の提供をし、婚活の手助けをし続けること15年。微力ながら、少子化対策及び高齢者福祉の一躍を担っています。
婚活(若者、ミドル、シニア)パーティー、ファイル閲覧、紹介見合を定期的に開催中です。入会登録者総数は現在までに1165名、内、在籍会員数は男性350名女性250名(令和5年5月現在)に登る。
活動拠点の大津町、近隣の菊陽町、合志市、菊池市、西原村の各首長他の御臨席を賜り、令和5年度定期総会を開催しました。

NPO法人はっぴぃ・はっぴぃ定期総会
「私が私として生まれてきて良かった」
せいしとらんし熊本は、性教育学習事業を行う非営利活動法人です。主として、性犯罪予防のための教育と啓発活動を行っております。幼児・小学生の親子参加型の「いのちの学習」をメインに活動していますが、PTA講演会などでは「子どもの性への向き合い方」をお話したり、大人を対象とした性教育の学び直しの場を提供したりと、この世に生きるすべての人を対象にした性教育学習事業を展開しています。
その他、時代やニーズに合った【いのちの学び】を届けています。誰ひとり性犯罪の当事者にしない!という強い思いのなかで、行政や学校と連携をとりながら活動を広めていきます。
「性」は特別なものではありません。環境に左右されることなく、知識の格差がうまれなくて済む世の中にしていきます。

『地域食堂での親子(小学生)向け性教育の風景』
私たちは、日本文化の継承のために、熊本に遺された貴重な絵画文化財を護り、活かしていく活動に取り組んでいます。
現在取り組んでいるのは、江戸時代に参勤交代で使用されていた御座船「波奈之丸」(重要文化財「細川家舟屋形」)天井画の復元模写事業です。御用絵師らによって描かれた、金箔の輝く煌びやかな天井画171枚が現存していますが、それらは熊本の貴重な絵画文化財でありながら、舟屋形内部にあるため公開が難しく、市民にもあまり知られていません。
そのため私たちは、実物が描かれた当初と同じ素材・同じ技法により、肥後の草木花果が描かれた天井画 全171枚を完全復元模写し、広く県民に公開していく活動を3年計画で始めました。昨年秋のクラウドファンディングと寄付で金箔や顔料など画材代の資金は調達。今回はその展示のため、格天井を模した黒塗りの木枠に実物と同様、九曜紋の鍍金細工を施した飾り金具の仕様を予定しています。
ふるさとを想う皆さまのご支援を、後世に繋がる新たな文化財として、また、熊本城天守閣の復旧にも花を添えられるような展覧会を実現させたいと願っています。どうぞ宜しくお願いいたします。
ご支援の程よろしくお願いいたします。

波奈之丸(なみなしまる)内部・天井画
「NPO法人オハイエくまもと」は、障がいのある人もない人も一緒になって音楽やダンスを楽しみ、音楽の力で心のバリアフリーを目指すボランティアグループです。日頃は音楽やダンスが大好きなパフォーマー(主に知的・発達障がいのある人たち)に楽器演奏や歌、踊りを練習する場を提供し、音楽指導者が指導しています。その発表の場として年に1回、街の中心地などで道行く人も巻き込んで一緒に音楽を楽しむ「とっておきの音楽祭」を開催しております。
【使命】
1.NPO法人オハイエくまもとは、知的・発達障がいのある人たちを中心に、それぞれの地域で日常的に音楽(楽器演奏、歌、踊り)を練習し楽しむ場を提供します。
2.NPO法人オハイエくまもとは、知的・発達障がいのある人たちを中心とした日常的な音楽活動の発表の場として、あらゆる障がいのある人もない人も一緒に音楽を楽しみ、心のバリアフリーを目指す「オハイエくまもと とっておきの音楽祭」を開催します。

オハイエくまもととっておきの音楽祭は、障がいのある人もない人も一緒に音楽を楽しむ場を提供し、音楽の力で心のバリアフリーを目指す事を目的に開催しています。会場は熊本市街地(主に屋外)で、道行く人達とのふれあいの場所とし、それぞれの団体がダンスや歌、演奏を披露します。
阿蘇地域の自然環境と景観を守りながら、地域づくりを行う組織として、平成2年5月に設立しました。
阿蘇管内7市町村および上益城郡山都町(旧蘇陽町)が一体となり、地域振興、観光振興、環境・景観保全、情報発信など、公益認定を受けた以下の事業(公1~公3)に取り組んでいます。
公1「豊かな自然による世界ブランドの確立 ~阿蘇草原の維持・再生~」
ア.草原再生PR事業
イ.野焼き支援事業
ウ.阿蘇産品の振興
エ.世界ブランド事業の推進
公2「地域の元気再生による地域力向上」
ア.地域元気再生支援事業
イ.的確な情報の発信
ウ.阿蘇回帰運動への取り組み
エ.人材育成事業
公3「広域連携による競争力のある観光地づくり」
ア.新たな阿蘇資産の構築・推進
イ.何度も訪れたくなる観光地域づくり
ウ.広域連動型観光まちづくり事業
【人材育成事業活動事例】
ビジネスを通じた地域課題の解決を目指す!!
あそ未来創造塾ホームページ
↡
https://miraisouzoujuku.aso-navi.com


そらふねの桟橋
あそ未来創造塾第4期生
◆キャッチフレーズは「広がる未来 つながる地域」◆
「いつでも・どこでも・だれでも」スポーツに楽しめる環境の実現を目指しています。子どもから高齢者まで幅広い世代の人々が、それぞれの興味関心・競技レベルに合わせて、さまざまなスポーツに触れる機会を提供する地域スポーツクラブを原点として、地域の皆さんと共に地域社会の連携と明るく豊かな生活の実現に向けた取り組みのお手伝いをしています。
平成24年に法人設立。南関町におけるスポーツ団体等を統括し、南関町民及び町外の住民に対して、運動や住民の触れ合いの場の創出、健康増進、体力の向上及びスポーツ文化の振興などを通じて持続可能な地域の発展に貢献することを目的に活動しています。
◆寄付金を次のことに役立てます◆
(1)地域の子ども達の健やかな体づくりを支えるスポーツ環境の整備(共用スポーツ用具の購入、練習着製作費など)
(2)障がい者・障がい児が自分の住む地域でスポーツに親しめる環境の整備(共用スポーツ用具の購入、専門講師の招聘費用、地域指導者の研修費用など)

老若男女が健やかに支え合う人生をイメージ
熊本子ども囲碁普及会は、一人でも多くの子どもたちに囲碁を知ってもらい、楽しんでもらうことが、郷土熊本、そして日本の将来を担う子どもの健全育成につながるという理念のもと、熊本県内12の子ども囲碁教室を中心に普及活動をしています。
皆様からいただいたご寄附は、県全体の子どもを集めた交流囲碁大会の開催や、幼稚園・地域公民館での囲碁教室への講師派遣、小学校の放課後児童クラブで囲碁を教える活動などに活用させていただきます。

交流大会で対局を楽しむ子どもたち
当法人は、熊本の地域活性化に寄与する事業を支援することにより、一人でも多くの自立型市民(暮らし人)を育み、熊本の地域社会の活性化に寄与することを目的として、熊本暮らし人まつり「みずあかり」を開催しています。「みずあかり」は、「竹」「火」「水」「ろうそく」といった熊本の資源を生かした灯りの祭典です。秋の夜、熊本城周辺に2日間で約5万4千個のろうそくが灯ります。
熊本の魅力を再発見し「ここに暮らす喜びと、切なさまでも共感できる市民と地域でありたい」というコンセプトのもと、2004(平成16)年にスタートしました。運営は、延べ約6,000人のボランティアの手によって行われます。竹灯籠の制作、設置、当日の運営、その後の片付けまで、地元企業、市役所や県庁の職員、自衛隊、学生、一般市民ボランティアなど多くの人たちの協力によって成り立っています。
皆様のご支援をよろしくお願いいたします。

みずあかり風景(市民会館前)
―精神障がい者等の社会生活を支援しています―
(1)精神障がい等を持ちながら地域で生活している
方へ、昼間の活動の場(居場所)を提供し、軽
作業などを通じて仲間と触れ合うことにより、
社会との繋がりや生活のリズムを整えることを
支援しております。
(2)保護者と利用者の両者が高齢化する中で、親な
き後の単身生活を支えたいと、3年前から昼食
の提供を始めました。
ご支援のほどよろしくお願いいたします。


「恵方巻」作りの実習
一般社団法人Arts and Sports for Everyone
私たちの団体は、障害のある人もない人も日常的に芸術やスポーツ活動を一緒に楽しめる共生社会の実現をミッションにしています。
具体的な活動としては、
(1)障がい者スポーツのボッチャの体験会を学校、商店街、イベント、老健施設などで随時開催することで、市民の方々に障がい者及び障がい者スポーツの理解をしていただいています。
(2)障がいをお持ちの皆さんが互いに交流し、障がいをお持ちではない方々と一緒にチームを作ってプレーする機会を提供するレクレーションボッチャの大会「楽球甲子園」を開催しています。
その他、障がい者及び障がい者の芸術やスポーツ活動を知っていただくために、フォーラムやトークショーを不定期に開催したり、芸術やスポーツ活動に取り組む団体の支援をしています。今年は秋に東京でデフリンピックが開催されるので、その認知度を上げる活動を計画中です。

第5回楽球甲子園に参加された皆さん
貴方もサポーターに!
スペシャルオリンピックス(So)とは、知的障がいのある人たち(アスリート)に年間を通じて日常的なスポーツトレーニングとその成果の発表の場である競技会を提供し、社会参加をサポートしている国際的なスポーツ組織です。
日本のSo活動は、1991年の世界大会に熊本の10歳のアスリートと一人のボランティアコーチが参加し銀メダルを獲得したことに始まり、全国に広がっていきました。県内10の地域で17種目の競技プログラムを展開し、毎年県大会を開いて、4年に一度の夏季・冬季の全国大会や世界大会に選手団や応援団を派遣し、チャリティー活動や各種イベントも活発に実施して地域社会や他団体との交流を深め、アスリートの可能性を広げています。
2025年3月にイタリア(トリノ)で開催された冬季世界大会に2名のアスリートがスノーシューイング競技に出場し銀メダル1個を獲得しています。貴方も世界へ羽ばたくアスリートを支援していただけませんか!

Soの競技会では、性別、年齢、競技能力などによってグループ分け(ディビジョニング)を行い、全てのアスリートに勝つチャンスが与えられるように考えられてます。
認定NPO法人トナリビトは、すべての子ども・若者が「自分は愛されるために生まれてきた!」と思える未来を目指し「Love First(ラブ・ファースト)」を土台に関係づくりを重視した支援を行っています。この熊本にも、親と暮らせず施設で育つ子どもや、様々な事情で家に帰れない若者がいることをご存じですか?皆様から頂いた寄付を活用し、児童養護施設経験者や福祉の狭間で支援が得られず、孤立化・生活困窮化する若者を対象に、『自立支援シェアハウスIppo』『緊急短期シェルターokioki』『相談窓口・居場所スペースおとなりさん』の運営を実施しています。 トナリビトにたどり着いた若者たちは、安心できる場所を得て、一息つき、自分らしく生きる次のステップを目指しています。
【事業内容】 (1)子どもの権利擁護推進、(2)自立支援(生活訓練、住居支援等)、(3)学習支援、(4)就労支援、(5)普及啓発、(6)支援者育成などを事業として展開しており、親を頼れない若者を対象とした生活用品の支援「お譲り品プロジェクト」、 一人暮らし生活支援宅配便「おとなり便プロジェクト」、成人式の着付け・写真をプレゼントする「Kimonoプロジェクト」等を企画開催しています。
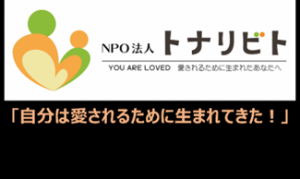

すべての子がそう思える未来を目指して
「シェアハウスの夕食風景」
熊本いのちの電話は、つらさや悲しみなど、人間であればだれもが抱える悩みを匿名で話すことができる相談電話です。
死んでしまいたい・・・と思うほど心が追い詰められてしまうときでも、いのちの電話は24時間365日、年中無休でお電話をお待ちしています。
2024年度は、10260件の相談が寄せられ、そのうち約14%が死を考えるほどの非常に深刻な内容でした。電話を受ける相談員は、現在約140名が活動していて全員が無償のボランティアです。そして、だからこそ、心からの温かい対応で優しくよりそっています。お電話をくださった方々の気持ちが少しでも軽くなり、一人でも自殺者が減ることを願って活動を続けています。
この活動は個人・団体・企業の皆さまのご寄付で運営されていますが、相談活動を維持するための資金が不足しています。優しさに満ちあふれたこの活動に、どうか皆さまのお力添え、ご支援をお願い致します。

電話相談室で相談を受けている様子
ブリッジフォースマイルは、親を頼れない子どもたちの巣立ちを支援しているNPO法人です。
「親を頼れないすべての子どもが笑顔で暮らせる社会へ」
初めて一人暮らしを始めたときのこと、覚えていますか?
私たちは、親を頼れず、18 歳で自立を迫られる子どもたちに、彼ら自身の意思を主にし、できることを支援し寄り添っていくという方針で、キャリア支援や施設退所後のつながりを中心に、多くの自立支援プログラムを実施してきました。
児童養護施設等および地域の支援団体や専門家と連携をとり、地域サポーター(ボランティア)方の支えにより活動を推進しています。
これからも社会的養護下の子どもたちや施設を退所した若者たちに、より良い支援を行うため、それぞれの特長・専門性を持つ社会資源にも積極的に橋渡し(ブリッジ)をし、子どもたちがどんな環境で生まれ育っても、夢と希望を持って笑顔(スマイル)で暮らせる社会を目指して活動してまいります。
「親を頼れなくても、私は大丈夫」
子どもたちがそう言って心から笑えるようになるために、がんばるのは子どもではなく大人たちです。
親を頼れない子どもたちが、自分の未来をワクワクしながら描ける社会をつくるため、ぜひ力を貸してください。


ブリッジフォースマイル熊本拠点ロゴ
週2回みんなで夕食を作り食卓を囲みます。
「自立の店ひまわりパン工房・カフェ」では、心と体に「やさしいパン」を作っています。
素材にこだわり丁寧に日々真心を込めてお客様に喜ばれる商品が提供できますようにチャレンジドと支援員、ボランティアが力を合わせて努力を重ねています。
チャレンジドとは、「障がいをもつ人」を表す米語「挑戦という使命や課題、挑戦するチャンスや資格を与えられた人」を語源としています。障がいをもつゆえに体験する様々な事象をポジティブに活かしていこうという思いが込められています。
チャレンジド達は純粋な心でとても真面目にお仕事に取り組んでいます。その姿からははっとさせられるような尊さ、きらりと光る感性がかいま見れます。それぞれがもつ個性が活かされて、ひまわり全体がもっともっと達成感のある魅力的な就労の場になりますように、皆様の応援を宜しくお願い致します。

応援よろしくお願いいたします!
児童虐待など様々な理由により家庭で暮らせなくなり、社会的養護を必要とする子ども達が家庭・地域社会で育まれ、自立した社会の一員となることが当会の事業であり、その広報・啓蒙活動を目的に活動しています。皆さまのご支援をどうぞよろしくお願いいたします。
家族と暮らせない子どもたちは全国に約45,000人、熊本には約630人います。そのような子どもの約13%が里親と暮らしています。もっと里親を増やし、すべての子どもたちに温かな家庭を提供したい、それが優里の会の願いです。

パネル展の様子
NPO法人ガットは、不登校児童生徒(小中学生)の学習をサポートする「ガット教室」を運営しています。
学校に通えない児童生徒は増加の一途をたどっています。子どもたちは、将来の日本を支える宝です。そんな子どもたちが、学びを継続し、自立し、社会の一員として活躍できるよう、また、自己実現が図れるよう活動しています。
朝から社用車で自宅まで迎えに行きます。「ガット教室」に到着すると、15分間読書の後、2時間または3時間の教科学習を行います。休憩時間には、ウォーキングや運動、野菜作り、木工製作なども希望を受けて行います。学習が終わると、社用車で自宅まで送ります。
「ガット教室」で学んだお子様は、高校に合格したり、学校に復帰したり、学力を高めたりして自立に向かっています。家に引きこもるのではなく、外に出て学ぶ良さとその効果を、子どもたちの成長から実感しています。
みなさまのご支援で、より利用しやすい体制を整えたいと思っております。温かいお力添えを何卒よろしくお願い申し上げます。

学び舎内
障害がある方の観光や旅行の支援、情報提供を行っています。県外から観光に来られる方のために、旅行ガイドのスキルのあるヘルパーの育成、手配、観光地における障碍者の受け入れ、おもてなし研修など幅広く観光のUd化に取り組んでいます。
ご寄付頂いた資金は県内の様々な観光地のUd情報を取材、発信するために大切に使わせていただきます。

砂浜用車いす支援の様子
自立応援団は熊本市北区で、20年以上、障害のある方の自分らしく『はたらく』と自分らしく『くらす』を応援してきました。
2002年からはNPO法人として、就労継続支援A型事業所、就労継続支援B型事業所、訪問介護サービス、グループホーム運営、また、住宅の確保に困っている障害者、高齢者の住み替えを支援するための情報提供・相談を行う居住支援等を行っています。
皆様からのご寄付は、新しい仕事に挑戦するための設備費や研修費、グループホームでより快適に過ごせる環境づくりに役立てられます。みなさまの温かいご支援をよろしくお願いいたします。

自分らしく「はたらく」と自分らしく「くらす」を応援
私たちは「障害」があっても無くても当たり前に地域で暮らすこと、つまり『地域共生』を目指して活動している団体です。それぞれの違いを受け入れ合う豊かさを大切にし、人と人が繋がり合う関わりを大切にしています。
とら太の会を母体に、多機能型事業所みのり(就労継続支援B型・生活介護)、地域型・認可外保育所ありんこ園、放課後児童クラブとら太・タイムケア(障害児放課後預かり事業)、ふれあい農縁・ホーム、計画相談事業所とら太、児童家庭支援センターとら太を運営しています。
小さな子どもの頃から色んな人と出会い関わりあうことで自然に互いを受入れ思いやれる人に成長していきます。私たちはこのことを『共生の種まき』と言っています。これからも共生の種を蒔き続け、いつの日か『地域共生』という言葉が死語になるように活動し続けていきます。
応援よろしくお願いします。

『地域共生』を目指して活動中!
当法人は、設立当初における地域の障がい者・高齢者等の社会的弱者のちょっとしたお手伝い(買い物代行・草取・電球の交換・簡単なリフォーム等)から出発し、幼少期の子供達への観劇会(無料招待)、本妙寺参道での門前市の開催、厚労省主管の未就労者に対する基金訓練制度(技能・技術力を体得)を経て、12年前より福祉部門を設け、障がい者の就労継続支援B型事業所とグループホームを開所して、今日に至っています。
この経緯をご覧戴ければお解りのように、一貫して社会的に援助が必要と考えられる皆様が、「肉体的にも、精神的にも、そして社会的にもすべてが満たされた状態」に到達する為の活動に取り組ませていただいております。福祉事業以外にも過去7年程前より、全国的にも生物の多様性にも物議を醸す外来魚の駆除にも取り組み、2018年熊本県知事より「熊本環境教育賞」と、2020年には保全活動部門で「環境大臣賞」の栄えある賞を賜っています。


老人保健施設のベットメイク
人参の皮剥ぎ作業
NPO法人ひのくにスマイルプロジェクトは熊本県菊池市に拠点を構え、ひのくにスマイル食堂(こども・地域食堂)やフードバンクひのくに(フードバンク活動)、子育て講座の開催や子育て・不登校相談などの相談援助活動、熊本県内のこども食堂ネットワーク、災害救援活動などを通して、こども達に笑顔を届ける活動をはじめ、孤立防止や災害時にも迅速に動ける体制づくりに努めております。よろしくお願いいたします。
各活動の詳細は当団体HP:https://hinopro.jp/
をご覧ください。

子ども食堂に来ている子ども達の様子
熊本県の「認定就農研修機関」です。
農業の知識や技術はなくても、 農業をこれからの新しい職業として始めたいという強い希望や夢を持っている人。
「農」的生活に関心を持ち、 ふるさとで農業に携わった生活をしたいと思っている人。当センターは、このような農業を志す人を新規就農者や農的生活者として育成し、自立させるために現役農業経営者が中心となって研修・指導を行い、日本の農業の未来を担う人材の育成を目指してます。実践主義に基づいた農業研修でプロ農家の育成を目指します。研修修了生は施設園芸、露地野菜、果樹、畜産、有機など様々な分野において全国各地で活躍してます。
知識や技術、経験は無くても農業を始めたいという強い希望・夢があり、前向きで協調性・積極性のある就農希望者のみ募集します。10代~40代、脱サラ、新卒、Iターン、Uターン、農家子弟など様々な人材が新規独立就農しています。当NPOの農家から実践的農業経営ノウハウを学びませんか!

日本の農業人材育成の為に、是非ご協力をお願いいたします。
我々水俣青年会議所は、水俣・津奈木・芦北地域の20歳から40歳までの青年経済人で構成されており、地域のリーダーを育成すること、地域の社会課題を解決するために行動すること、そしてその過程で多くの経験を糧に自己成長を積み重ねることで、地域の明るい豊かな社会の実現を目指す団体です。
本年、水俣の夏の風物詩となった「こいのぼり事業」は50周年を迎え、今年も子供たちの健やかな成長とこれからの未来を明るく照らしてくれることを願い、水俣川沿いに鮮やかなこいのぼりが掲げられました。
更にまちづくり事業においては、各年献血事業や高校生向けの学習プラットフォーム形成事業、青少年育成キャンプ事業などその年年の地域の課題を見出し、課題解決の一助となることを目指し活動しています。
しかし会員数が現在12名という少数団体のため、資金面において常に不足の状態であり、木の伐採や建て込み、こいのぼりの制作・寄付活動など事業内容においても最大限の活動を展開することができない状態にあります。
今後の活動を幅広く展開し、更なる地域の明るい豊かな社会の実現を目指すためにも、是非皆様の寄付をお願い申し上げます。

本年で50周年を迎える「こいのぼり事業」(水俣川沿い)
特定非営利活動法人熊本県地域こども食堂支援センター Tsudou・Net
私たち「熊本県地域こども食堂支援センターTsudou・Net」は、熊本県内の「地域食堂・こども食堂」の運営を支援する団体として、2016年2月に発足しました。
ビジョン…地域食堂・こども食堂の運営を支援し、地域全体で子どもたちの成長を見守り、みんなが支え合い、Tsudou(集う)環境を作ります
ミッション…地域の人々が世代を越えて集まり、温かなつながりの中で支え合う社会を築くことです。Tsudou・Netは、誰もが安心して集える場所を創り、未来を担う子供たちが健やかに育つ環境を地域と共に育んでいきます。
事業内容としては、
🍚こども食堂を始めてみたい方へ
食堂を開設する際の立ち上げ支援・アドバイス
🍚こども食堂を運営している方へ
・運営にあたってのご相談対応・アドバイス
・情報発信・研修会・食堂運営者同士の親睦交流・
・各種申請のお手伝い、他伴走支援
🍚こども食堂を応援したいと考えている方へ
県内の食堂×企業・個人×ボランティアとのマッチング
🍚自主事業
・地域の文化や伝統、郷土食の継承事業
・「熊本県地域福祉計画」の「地域の縁がわづくり」「地域の結いづくり」等の側面支援
・農水産業の六次産業化の支援事業
・「防災拠点×こども食堂」の啓蒙活動

こども食堂の様子(一番上は食堂のスタッフのみなさんです)

